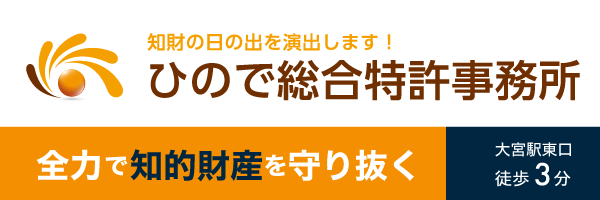さいたま市でメディアアート展 地名の物語をAIで映像化し障子に投影

和紙障子プロジェクションマッピングのメディアアート展「大宮曼荼羅(まんだら)2025」が8月23日~26日、さいたま市の盆栽村100周年に合わせて、盆栽四季の家(さいたま市北区盆栽町)で開かれる。
同展はアーツカウンシルさいたま文化芸術都市創造助成事業の一つで、さいたま国際芸術祭2023の公募プログラムで選ばれた「大宮曼荼羅」のリメーク作品を展示する。
「和紙障子」には厚口の和紙を使い、複数枚重ねて映像光を透過しにくくすることで、障子の表と裏に異なる映像を投影する。表面にはさいたま市内の120の地名と伝説をAIでイラスト化し、それぞれの障子枠に異なる映像を、裏面には、さいたま市の現在の風景をコラージュ化した映像を投影する。「特徴がない」と言われることが多いさいたま市のアイデンティティーを、過去と現在を同一の障子枠内で表現することで、再考する試みとなっている。
作者で映像作家の坂根大悟さんは旧大宮市出身。学習院大学文学部史学科で映画史を研究し、卒業後は社会人を経て、現在は東京芸術大学大学院映像研究科に在学する異色の経歴を持つ。土地の持つ歴史や都市の歴史をリサーチしながら、相反するものが共存する「陰陽太極図的メディア空間」をテーマに、立体や映像などを組み合わせて作品を制作している。今回の展示も、さいたま市の過去と現在が共存するメディアアート展となる。
坂根さんは「知らない街に行き、郷土資料館で歴史をインストールしてから街に出て、街の現在を見ると、過去と現在のズレが見えて気持ちがいい。そんな経験を伝えたくて、このメディア(和紙障子)を選んだ。一画面の映画だと物足りず、120スクリーンを同時に表示したらどうなるかを試したかった」と話す。
制作に当たっては、埼玉県の地名誌や合併前の市史を調べ、作者の想像も加えながら、さいたま市内の120の地名や伝説に基づいた画像をAIで3000枚以上作成。その中から120枚を選び、動画にした。
「面白さは日常に転がっている。生きる土地の面白さを知り、気付くことは社会参加へのきっかけにもなる。同展を通じて鑑賞者自身の世界認識が広がるような未体験の感覚に触れてもらえれば」と坂根さん。実行委員会の鈴木知佐子さんは「前回の『大宮曼荼羅』再展示を望む声に応え、開催が実現した。本当に良い作品なので、一人でも多くの方に見てほしい」と呼びかける。
展示時間は10時~18時。入場料は300円(小学生以下無料)。